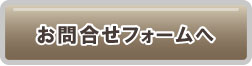バックボード(バックパネル)のデザインを選ぶ際の大事なポイントとは?
2020年08月04日
ノウハウ
バックボード・バックパネルといえば、記者会見やイベント、フォトスポットや動画配信の背景としてよく使われている大型バナースタンドです。
よく使われているのは見かけるけれど、いざ必要となった時、はじめは何からどう準備すればいいのか困ってしまうこともあるのではないでしょうか。
今回はバックボード・バックパネルを選ぶにあたってはじめてでも失敗しないように、用途別に人気のデザインやおすすめのバックボードタイプご紹介します。

バックボードを制作するにあたり、必ず必要になってくるものがデザインデータです。
そして、もっとも準備が難しいのもデザインデータです。
一般的に印刷用のデザインデータを作成するIllustratorソフトをお持ちで、尚且つ自分で使いこなせるという方は別ですが、そうでない多くの場合はデザインを外注をしたり、データ作成を請け負っている業者やショップで購入したりすることが必要になってきます。
そうなるとまず気になってくるのはデザイン費ですよね。
特に初めて利用する方にとっては、デザインの外注というとかなり高額なイメージもあると思います。
では、実際にはどのようにして金額が決まるのか、3つのポイントを挙げてご紹介していきます。
デザイン費用は、大きさではなく内容で決まります。
そのため、デザイン費を節約したいからと言ってバナーのサイズを小さくする必要はないといえます。
(出力費用は大きいほど高くなります。)
基本的にはこれらの要素が多いほうがデザイン費は上がります。
無地の背景にロゴだけを乗せたシンプルなデータのデザイン費は安価ですが、背景写真を入れたり、テキストや商品画像などを追加したりと、デザインを構成する要素が増えるにつれてデザインデータ作成費は上がっていきます。
また、それらの要素にどれくらいデザインアレンジをするかも大きく費用に関わってきます。
企業イメージや商品イメージなどをもとに、全くのゼロからデザインを依頼した場合、打ち合わせなどの必要性から時間もかかりますし、多くの場合かなりの高額になります。
逆に言えば、デザインのイメージ(ラフデザイン)をしっかりと練ったうえで、写真やロゴなどの素材もすべてご支給いただければ、費用を大幅に抑えることができます。
バナースタンド研究所ではネットショップという性質上、後者のデータ作成に限りご依頼を承っております。
ラフデザインと素材をご支給いただける場合、お得に出力用データを作成致します。
はじてめのバックボード制作でも困らないよう、人気のデザインパターンとバックボードのおすすめタイプをシーン別にご紹介します。

<デザイン>
テレビで見る記者会見の際に必ずと言っていいほど採用されているのが2色の背景を互い違いに配置し、その上にロゴやテキストを並べた基本となるシンプルな市松模様のデザインです。
基本的には背景に合わせて1~2種のロゴやテキストが入る場合が多いですが、応用として3種以上のロゴを配置したり、部分的に市松模様にしたりといった事例もあります。
最近では、動画配信の背景として市松模様を採用する事例も増えてきています。
市松模様のデザインは、記者会見以外にも各種イベントやキャンペーンなど、活躍する機会の多い優秀なバックボードです。
<おすすめタイプ>
複数人が横に並ぶような記者会見では横幅3Mに対応できる幅広の「ウォーリー」がおすすめです。
設置・収納・持ち運びも簡単なので必要な時にさっと準備できます。

<デザイン>
非常に多くの人で賑わう展示会では、道行く人に企業名や商品特徴など一目で伝えたいことが伝わるシンプルで説得力のあるバナーが必要とされます。
そのため企業ロゴや商品画像を大きく配置したインパクトのあるデザインがおすすめです。
<おすすめタイプ>
大きな展示会では圧巻の高さ3M「ウォーリー3 High」など、アイキャッチ効果抜群の大型バックボードがおすすめです。
また、横に広いブースであれば連結できるテンションファブリック「Harry(ハリー)」がおすすめです。

<デザイン>
商品のPRイベントはもちろん、体験型イベントや屋外イベントなどでも、バックボードは様々な使い方ができます。
継ぎ目のない1枚のスクリーンで出力できるバックボードは、大きく商品写真やイベント名を入れてPRしたり、前に人が立ち記念撮影できるデザインにするのも面白い使い方です。結婚式などでも使えます。
<おすすめタイプ>
背景用に大きなパネルを用意するとなると設営も大掛かりになるうえどうしても時間もコストもかかりますが、バナースタンドのバックボードならコンパクトに収納できて設営や撤去もスピーディー、さらにスクリーンの取り外しができるため本体は繰り返し使うことができて経済的です。
デザインをきれいに見せたい場合には、しわが目立たずフレームレスな表現ができるテンションファブリックタイプの「Harry(ハリー)」、
収納がコンパクトで設営が素早くできるロールアップタイプの「i-LooK200(アイルック200)」「くるりんⅡ200」、
屋外イベントではウォータータンク付きの「アルファ-エコ」がおすすめです。
いざ購入した後に「うまく使いこなせない」「イメージと違う」「別のタイプにすればよかった」とならないために、デザインや目的に合わせてしっかりと仕様を選ぶことが大切です。
その方法によってメリット・デメリットがありますのでバックボードを選ぶ際のポイントとして押さえておくと失敗しません。

・保管方法によってはスクリーンにしわがつきやすい

・スクリーンの取付にややコツがいる

・収納時にスクリーンを取り外す必要がない
使用シーンや目的に合わせて最適なものを選びましょう!
当日になって使えない!とならないように、事前に使用可能なサイズを確認しておきましょう。
ロールアップタイプの「i-LooK」シリーズは、伸縮式の支柱を採用しているのでスクリーンの高さ調節が可能です。
デザインを工夫すればイベントごとに会場に合わせて高さを変えることもできるため、1台のバックボードで複数のイベントに使いたい!という場合におすすめです。
今回はバックボードに焦点を置いて、タイプの違いやデザイン、おすすめ商品などを ご紹介させていただきました。
商品選びに迷った際はぜひ参考にしていただければ幸いです。
バナースタンド研究所では今回ご紹介した以外にも、用途に合わせて様々なタイプのバックボードをご用意しております。
商品のことやデザインのことなど、ご不明点はお気軽にお問い合わせ ください。
記者会見や各種イベントに今や必須となったバックボード、用途に合ったあなたに ぴったりの1台を見つけましょう。
今回はバックボード・バックパネルを選ぶにあたってはじめてでも失敗しないように、用途別に人気のデザインやおすすめのバックボードタイプご紹介します。
<目次>
バックボードのデザイン費はどうやって決まる?

バックボードを制作するにあたり、必ず必要になってくるものがデザインデータです。
そして、もっとも準備が難しいのもデザインデータです。
一般的に印刷用のデザインデータを作成するIllustratorソフトをお持ちで、尚且つ自分で使いこなせるという方は別ですが、そうでない多くの場合はデザインを外注をしたり、データ作成を請け負っている業者やショップで購入したりすることが必要になってきます。
そうなるとまず気になってくるのはデザイン費ですよね。
特に初めて利用する方にとっては、デザインの外注というとかなり高額なイメージもあると思います。
では、実際にはどのようにして金額が決まるのか、3つのポイントを挙げてご紹介していきます。
ポイント① バナーの大きさとデザイン費用は比例しない
意外に思うかもしれませんが、多くの場合は大きなバナーでも小さなバナーでもデザイン費用に差はありません。デザイン費用は、大きさではなく内容で決まります。
そのため、デザイン費を節約したいからと言ってバナーのサイズを小さくする必要はないといえます。
(出力費用は大きいほど高くなります。)
ポイント② デザインに含まれる要素
デザインに含まれる要素とは、例えばデザインデータに配置する「背景」「ロゴ」「テキスト」「写真」「図形」などのことです。基本的にはこれらの要素が多いほうがデザイン費は上がります。
無地の背景にロゴだけを乗せたシンプルなデータのデザイン費は安価ですが、背景写真を入れたり、テキストや商品画像などを追加したりと、デザインを構成する要素が増えるにつれてデザインデータ作成費は上がっていきます。
また、それらの要素にどれくらいデザインアレンジをするかも大きく費用に関わってきます。
ポイント③ 支給素材の有無
あらかじめデータの一部をご支給いただくことで、データ作成費を抑えることができます。企業イメージや商品イメージなどをもとに、全くのゼロからデザインを依頼した場合、打ち合わせなどの必要性から時間もかかりますし、多くの場合かなりの高額になります。
逆に言えば、デザインのイメージ(ラフデザイン)をしっかりと練ったうえで、写真やロゴなどの素材もすべてご支給いただければ、費用を大幅に抑えることができます。
バナースタンド研究所ではネットショップという性質上、後者のデータ作成に限りご依頼を承っております。
ラフデザインと素材をご支給いただける場合、お得に出力用データを作成致します。
シーン別!バックボードのデザインとおすすめのバックボードをご紹介!
バックボードと一言で言っても、検索してみるといろんな種類が出てきてどれを選べばいいか困ってしまうことがあるかと思います。はじてめのバックボード制作でも困らないよう、人気のデザインパターンとバックボードのおすすめタイプをシーン別にご紹介します。
使用シーン① 記者会見

<デザイン>
テレビで見る記者会見の際に必ずと言っていいほど採用されているのが2色の背景を互い違いに配置し、その上にロゴやテキストを並べた基本となるシンプルな市松模様のデザインです。
基本的には背景に合わせて1~2種のロゴやテキストが入る場合が多いですが、応用として3種以上のロゴを配置したり、部分的に市松模様にしたりといった事例もあります。
最近では、動画配信の背景として市松模様を採用する事例も増えてきています。
市松模様のデザインは、記者会見以外にも各種イベントやキャンペーンなど、活躍する機会の多い優秀なバックボードです。
<おすすめタイプ>
複数人が横に並ぶような記者会見では横幅3Mに対応できる幅広の「ウォーリー」がおすすめです。
設置・収納・持ち運びも簡単なので必要な時にさっと準備できます。
使用シーン② 展示会

<デザイン>
非常に多くの人で賑わう展示会では、道行く人に企業名や商品特徴など一目で伝えたいことが伝わるシンプルで説得力のあるバナーが必要とされます。
そのため企業ロゴや商品画像を大きく配置したインパクトのあるデザインがおすすめです。
<おすすめタイプ>
大きな展示会では圧巻の高さ3M「ウォーリー3 High」など、アイキャッチ効果抜群の大型バックボードがおすすめです。
また、横に広いブースであれば連結できるテンションファブリック「Harry(ハリー)」がおすすめです。
使用シーン③ 各種イベント

<デザイン>
商品のPRイベントはもちろん、体験型イベントや屋外イベントなどでも、バックボードは様々な使い方ができます。
継ぎ目のない1枚のスクリーンで出力できるバックボードは、大きく商品写真やイベント名を入れてPRしたり、前に人が立ち記念撮影できるデザインにするのも面白い使い方です。結婚式などでも使えます。
<おすすめタイプ>
背景用に大きなパネルを用意するとなると設営も大掛かりになるうえどうしても時間もコストもかかりますが、バナースタンドのバックボードならコンパクトに収納できて設営や撤去もスピーディー、さらにスクリーンの取り外しができるため本体は繰り返し使うことができて経済的です。
デザインをきれいに見せたい場合には、しわが目立たずフレームレスな表現ができるテンションファブリックタイプの「Harry(ハリー)」、
収納がコンパクトで設営が素早くできるロールアップタイプの「i-LooK200(アイルック200)」「くるりんⅡ200」、
屋外イベントではウォータータンク付きの「アルファ-エコ」がおすすめです。
失敗しないバックボードの選び方とは?
一言にバックボードといっても、用途に合わせて様々な仕様のものがあります。いざ購入した後に「うまく使いこなせない」「イメージと違う」「別のタイプにすればよかった」とならないために、デザインや目的に合わせてしっかりと仕様を選ぶことが大切です。
ポイント① 設置方法で選ぶ
バックボードには、設置方法(スクリーンの取り付け方法)にいくつかのタイプがあります。その方法によってメリット・デメリットがありますのでバックボードを選ぶ際のポイントとして押さえておくと失敗しません。

「ウォーリー」
・最も一般的なマジックテープ取付タイプ・保管方法によってはスクリーンにしわがつきやすい

「Harry(ハリー)」
・テンションファブリックタイプでしわが目立たず綺麗な仕上がり・スクリーンの取付にややコツがいる

「i-LooK200(アイルック200)」/「くるりんⅡ200」
・ロールアップタイプなので設営、撤去がスムーズ・収納時にスクリーンを取り外す必要がない
使用シーンや目的に合わせて最適なものを選びましょう!
ポイント② 大きさで選ぶ
屋内のイベントや展示会などでは、展示物に高さ制限のつくものもあります。当日になって使えない!とならないように、事前に使用可能なサイズを確認しておきましょう。
ロールアップタイプの「i-LooK」シリーズは、伸縮式の支柱を採用しているのでスクリーンの高さ調節が可能です。
デザインを工夫すればイベントごとに会場に合わせて高さを変えることもできるため、1台のバックボードで複数のイベントに使いたい!という場合におすすめです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回はバックボードに焦点を置いて、タイプの違いやデザイン、おすすめ商品などを ご紹介させていただきました。
商品選びに迷った際はぜひ参考にしていただければ幸いです。
バナースタンド研究所では今回ご紹介した以外にも、用途に合わせて様々なタイプのバックボードをご用意しております。
商品のことやデザインのことなど、ご不明点はお気軽にお問い合わせ ください。
記者会見や各種イベントに今や必須となったバックボード、用途に合ったあなたに ぴったりの1台を見つけましょう。